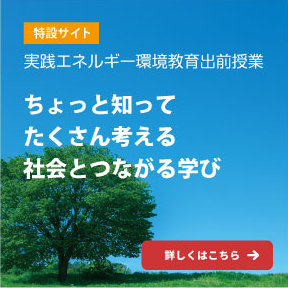よくある質問
- 一校に対する出前授業は1学年だけですか。一回の出前授業で複数の学年をお願いすることは可能でしょうか。
- はい。小学校なら1年生から6年生まで、中学校なら1年生から3年生まで実施可能です。特別支援学級や教職員の皆さま向けの授業も承っています。1学級のみの実施も可能ですが、ご希望に応じて複数学年や全学年にわたって行うこともできます。日程が2日以上にわたっても構いません。ご安心ください。滞在が複数日に及んでも、交通費や宿泊費などの経費をご負担いただく必要はありません。
- 学級ごと、もしくは、学年単位(2学級、3学級合同)で授業をしてくださいますか。
- はい。1学級だけでも、5学級あっても、それぞれ学級ごとに授業を実施いたします。学年単位での実施も可能ですが、人数や学級数によって進め方が変わりますので、ご相談ください。
- 小規模学校で、各学年1学級、10名に満たない学級があります。複式学級もあります。来て頂けますか。
- はい。小規模学校の少人数学級でも、複式学級でも、喜んで伺います。人数に関わらず学びの場を大切にしたいと考えています。1学級だけでなく、全ての学級での実施も可能ですので、ご検討ください。小規模中学校の場合は、3学年合同での授業も可能です。ぜひご相談ください。
- 全校21学級(と特別支援)の比較的大きな中学校です。3年生7学級をお願いしたいのですが、一斉授業は可能でしょうか。
- 一斉授業も可能ですが、子どもたち一人ひとりの学びを十分に深めるには、学級ごとに行う方が望ましいと考えています。私たちは同じ内容を繰り返し行うことに抵抗はありませんので、できるだけ学級ごとに実施することをおすすめしています。なお、過去には120名を超える合同授業を行った実績もございます。詳しくはご相談ください。
- 出前授業の内容(エネルギーと環境、ライフサイクルで捉えるエネルギー、放射線、地層処分など)は、小学生には難しすぎるのではないでしょうか。
- 100%の理解を求めるのは、専門家にとっても難しいことです。私たちは子どもたちの発達段階に応じて、わかりやすく工夫した授業を行っています。理解できる部分を、理解できる方法で、一緒に楽しく学んでいきます。
- 授業は講義のような形になるのでしょうか。
- いいえ。座学もありますが、一方的な講義ではありません。クイズ形式にして子どもたちが楽しみながら学べるよう工夫しています。小学校1–2年生や特別支援学級では、紙芝居のようなお話から始めます。どの学年でも複数の実験や体験が盛り込まれています。
- ブレインストーミングって何ですか。
- 集中して考え、多くのアイデアを出す方法です。脳内(ブレイン)に嵐が吹く(ストーミング)ように、集中して考えてアイデアをたくさん出す方法です。人数は問いません。ひとりでも、集団でもできます。出てきたアイデアに良し悪しの判断をせず、とにかく量を出すことを大切にします。アイデアを組み合わせたり変化させたりすることで、思いがけない発想が生まれることもあります。短時間で集中して行うのが特徴です。
- どんな実験をしますか。
- 1コマ(45分)の授業では、クイズ大会のほかに①霧箱実験、②測定実験、③放射線防護の3原則の体験、④ベントナイト水止め実験の観察などを行います。
2コマ連続(95~100分)の授業では、これらに加えて⑤「みゆカフェ」を行います。
①霧箱実験では放射線の飛ぶ様子を飛跡で確認します。
②測定実験では、放射線測定器「べーたちゃん」を使って身近なものを測定したり、遮蔽実験を行います。
③放射線防護の体験では「距離・時間・遮蔽」の3原則を体験します。
④ベントナイト水止め実験ではベントナイトという乾燥した粘土を使って、その特質を実験します。1コマ授業では講師が実験するのを観察してもらいますが、2コマ連続の授業では、実際に実験して体験します。
⑤「みゆカフェ」という新しいディスカッション手法を体験します。 - 「みゆカフェ」って何ですか。
- ブレインストーミングの効果を活用したディスカッションの手法です。複数のトピックについて話し合い、最後にまとめと発表を行います。名前は「幸式ワールドカフェ」の短縮形で、英語名は Me-You Café です。“Listen to me, listen to you(私の意見を聞いて、あなたの意見も聞かせて)”“Tell me, tell you(私に教えて、私もあなたに教える)”
――お互いの意見を交換し発展させる、偏見なく話し合う姿勢を大切にしています。 - 学校や教室、会場に放射性物質が残留して放射能が強くなることはありませんか。
- ありません。実験で扱う放射線源は自然界に存在するものです。授業前後で放射線量が増えることはなく、使用する放射性物質の管理には細心の注意を払っています。
- 参加者に危険が及ぶような実験ですか。
- いいえ。霧箱実験や測定実験で扱う放射線源は自然界に存在するもので、参加者に危険が及ぶことはありません。
- 来て頂くのに、費用はかかりますか。
- 費用はかかりません。ワークシートの印刷や「みゆカフェ」で使用する模造紙のご準備をお願いすることがありますが、実験教材、教材、交通費、宿泊費などをご負担いただく必要はありません。
- 学校側が準備しなくてはいけないものはありますか。
- パワーポイントを使用しますので、プロジェクター、接続ケーブル(HDMI)、電源、スクリーンや大型モニターなどをご準備ください。会場によってはマイクもお願いします。また、ワークシート印刷や模造紙のご用意をお願いすることがあります。ノートPCは持参します。
- 準備や後片付けを考えると、一回の出前授業にどのくらい時間がかかりますか。
- 30人規模の学級を例にすると、1コマ(45分)の場合は準備に約1時間、後片付けに約45分かかります。2コマ(連続)の場合は、それぞれ約1時間程度かかります。授業と授業の間は、1コマなら少なくても5分程度、2コマなら15分程度空けていただけると助かります。
- どういった教室/会場が必要ですか。例えば、理科室でないといけませんか。教室や会議室、体育館で実施することも可能ですか。
- 基本的に室内で電源が確保できれば実施可能です。学校でしたら、理科室・教室・会議室・体育館などで行えます。パワーポイントを使いますので、プロジェクターやスクリーン等をご準備ください。直射日光の当たらない環境だと霧箱実験が見やすくなります。2コマの場合は模造紙を広げられる机やテーブルがあると活動しやすいです。過去には公民館の一室や喫茶店を借りて実施した例もあります。
- 教室やランチルーム、校長室などで、子供たちと給食を供にしていただくことは可能でしょうか。
- はい。喜んでご一緒させていただきます。ただし、準備や後片付けとの兼ね合いもありますので、事前にご相談ください。
- 教材を買わされることはありませんか。
- ありません。必要に応じて教材準備のアドバイスは可能です。
- 授業の後で、学校の先生方と出前授業の講師の方と意見交換をすることはできますか。
- はい。大変ありがたい機会です。ぜひ意見交換をさせていただければと思います。
- 保護者の参観や公開授業、親子教室は可能ですか。
- はい。可能です。事前にご相談ください。
- マスコミが取材に来ても大丈夫ですか。
- はい。可能です。撮影は子どもたちのプライバシーにご配慮ください。授業の妨げになる撮影や行為はご遠慮願います。授業直後のインタビューについては、状況により応じられない場合もあります。ご相談ください。
- 学校のホームページに講師の写真入りで掲載しても構いませんか。
- はい。小中学校などの公式ホームページであれば掲載していただいて構いません。
- 希望した日程で、必ず来て頂けますか。
- できる限り調整いたします。ただし、すでに他校の予定が入っている場合や近隣で先約がある場合は、日程のご調整をお願いすることがあります。
- 講師は何人来られますか。授業が複数日に及ぶ場合はどうなりますか。
- 通常は1~2名ですが、授業補助者を含めて複数名伺う場合もあります。その場合は予めチームEEEより連絡させていただきますが、その際も交通費・宿泊費をご負担いただくことはありません。滞在が複数日に及んでも同様です。
- 学校や団体が負担すべきことは何ですか。
- 金銭をお願いすることは一切ありません。ご用意いただくのは、ワークシート印刷(A4・1人1枚)、みゆカフェ用の模造紙など、そして会場設備(プロジェクター、スクリーン、電源など)です。直射日光を避けられる環境ですと、霧箱実験で放射線の飛跡を確認しやすくなります。
- 授業は学校のどの教科に位置づけられますか。
- 総合学習、学級活動、理科、道徳、家庭科、社会科など切り口によってさまざまです。多くの小学校では、総合学習や理科、社会、学級活動の時間に行っています。
- ベントナイト水止め実験の「ベントナイト」って何ですか。
- 天然に産出する粘土の一種で、火山灰が堆積し変質してできた鉱物です。膨潤性(水を吸ってふくれること)・粘性(水分を含むと粘土のように自由に形を作れること)・吸着性(水分を含むと物質を吸いつけること)など数多くのユニークな特性を持っています。身近なところでは、化粧品(特に洗顔料)に、土木・建築・鋳造・土壌改良など、様々な分野の産業で使われています。授業では、高レベル放射性廃棄物の地層処分に関連して、その特性を実験で体験します。
- 高レベル放射性廃棄物って何ですか。
- 原子力発電の過程で生じる、非常に強い放射能を持つ廃棄物です。一般的には、原⼦⼒発電所で使い終わった燃料(使用済み燃料棒)をリサイクル(再処理)する際に残る廃液(再利用できない高い放射能を持つとても危険な液体)を、ガラスと融かし合わせて固めたもの【ガラス固化体】を高レベル放射性廃棄物と呼んでいます。とても高い放射能を持っているため、家庭から出る普通のゴミのように捨てることができません。日本でもまだ処分場所が決まっていません。
(なお、原子力発電で使い終わった「使用済燃料棒」も、そのまま直接処分される場合は高レベル放射性廃棄物となります。日本では使用済燃料棒を直接処分せず、再処理しています。) - ガラス固化体って何ですか。
- 原⼦⼒発電所で使い終わった燃料(使用済み燃料棒)をリサイクル(再処理)する際に残る廃液(再利用できない高い放射能を持つとても危険な液体)を、ガラスと融かし合わせて固めたもののことを言います。 高レベル放射性廃棄物のことです。
- なぜ、原子力発電のゴミ【高レベル放射性廃棄物】について考えないといけないのですか。
- 日本では1966年(原子力発電が始まった年)から現在(2024年)までに、原子力発電が累積発電電源構成(どのようなエネルギー資源を使って発電したかの累計)の約18〜24%を担っていました。日本にはすでに2,530本のガラス固化体があり(2025年3月)、今後さらに増え続けます。これまで原子力発電で使われた燃料を全て再処理し、ガラス固化体にしたと仮定すると、その量は、すでにガラス固化体となっている2,530本との合計で、約27,000本になります(2025年3月末時点)。 原子力発電所の稼働状況にもよりますが、このゴミは増えることはあっても減ることはありません。 高レベル放射性廃棄物は非常に高い放射能を持ち、家庭から出る普通のゴミのように捨てることができません。 だからこそ、私たち一人ひとりが処分方法について真剣に考える必要があります。
- なぜ小学生や中学生が地層処分について勉強するのですか。
- 世界各国でさまざまな処分方法が検討されてきましたが、「地層処分」が最適な方法であることが、国際的に共通な認識となっています。日本でも高レベル放射性廃棄物の処分方法として地層処分を進めることになりました。この事業は、調査から建設・操業・閉鎖まで100年以上に及びます。だからこそ、これからの社会を担う子どもたちにも学んでもらうことが大切です。私たちは、「どうして地層処分が良いのか」「本当に地層処分でよいのか」他の処分方法も検討したうえで、総合的に考える必要があります。
- 出前授業は大人向けにも可能ですか。
- はい。高専・大学生、地域の方々(婦人会や子供会など)にも実施しています。エネルギーと環境をライフサイクルで捉えるという考えに興味を持ってくださったグループがあれば喜んで伺います。ご相談ください。
- 「みゆカフェ」だけをお願いすることは可能ですか。
- はい。セミナーとしてご紹介も可能です。ただし無料で伺う場合は、エネルギー環境教育とセットでお願いしています。45分プラスで、ぜひエネルギーや環境についても一緒に学びましょう。
- 日本語以外でも授業をしていただけますか。
- はい。英語での実施が可能です。ワークシートやスライドの準備が必要ですので、申込時に「英語での授業を希望している」とお伝えください。
- 他にも質問があります。
- ページ上部のオレンジ色の「お問い合せ」からお問い合せください。お待ちしています。